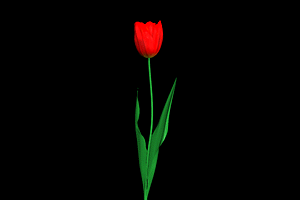
これから説明するのに左の花(チューリップ)を使うよ。
色がついていると説明が少し面倒になるので、次のように、白い造花にしたいと思う。
えっ、どうしてかって?まあ、講座を最後まで読むときっとわかるから、気にしない、気にしない、、。
|
|
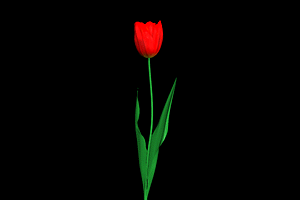 |
これから説明するのに左の花(チューリップ)を使うよ。 色がついていると説明が少し面倒になるので、次のように、白い造花にしたいと思う。 えっ、どうしてかって?まあ、講座を最後まで読むときっとわかるから、気にしない、気にしない、、。 |
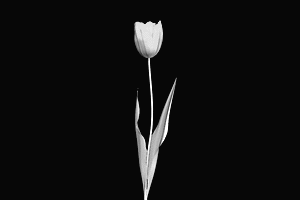
|
さて、部屋の中に、左の花(造花)をおいたと考えてね。 窓から光が入らないようにして、電気も消す。つまり本当の真っ暗にしよう。 さあ、この花を見てちょうだい。 |
| あったり前じゃん。真っ暗だから見えるわけないよな。何考えてこんな問題だしてるの?って逆に質問されそうです。 |
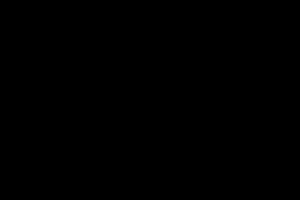
|
そうです。正解です。左のように真っ暗です。 でも、この中には確かに花がありますよね。手でさわってみましょう。ほら、あった。 |
 |
頭の上のライトを付けてみます。ほら、見えた。 あったりまえだよね。 でも、これをくわしく考えると、 ライトの光が物体にあたって、はねかえった(反射した)光が目に入ったとなる。 わかるよね。 |
| 赤く見えるのは、赤いライトをつけたから。何色でもいいんだけど、ホログラム撮影には赤いレーザーを使うことが多いんだ。そこで赤いライトを使って説明するよ。 |
 |
上の方から見てみよう。形が変わったね。 あったりまえじゃん。 さて、ここで、光の進む向きってことを考えてくれないかな。 見えるってことは、光が物体から飛んできて、目に入ったってことだよね。 つまり、最初は前に光が飛んできて、今度は上の方へ飛んできたということになるよ。 |
 |
今度は下の方から見てみよう。また形が変わった。 これも光の進む向きを考えて見てよ。 光が下へ向かったってことだよ。 |
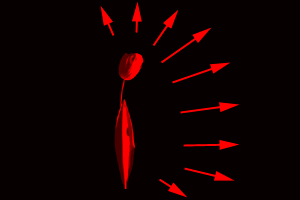
|
つまり、物体からは左図のように、上へも前へも、下へも光が飛び出しているってことだよ。 見る位置を変えるたびに光の向きが変わるんじゃないよ。見る人がどこにいるかに関係なくあちこちに光が飛び出しているんだ。 左図では上下にしか光の向きを描いていないけど、左右へも同じように広がって進んでいるんだ。四方八方へ進むんだ。わかるよね。 |
| チューリップの形が変わったのは横からみた図だからだよ。 |
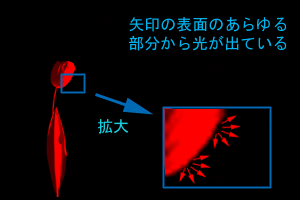 |
さらに、物体の一部を拡大してみるよ。 とんがった部分から光が四方八方へ進んでいることがわかるよね。 さらに、その上の部分でも同じように四方八方へ進んでいる。 この2つの部分は離れて描いているけど実際は原子や分子の大きさまで小さくなるんだ。物体の表面全体の小さな原子や分子1つ1つから光が四方八方へ飛んでいる。 頭の中でよくイメージしてごらん。 |
|
もうちょっと、書くよ。 下図のように物体表面から四方八方へ光が飛び出していることがわかるよね。 図では6つの部分からしか光が飛び出していないけど、実際は原子・分子の大きさの間隔で光が飛び出しているんだよ。 そして、飛び出した光はどこまでもまっすぐ進む。 |
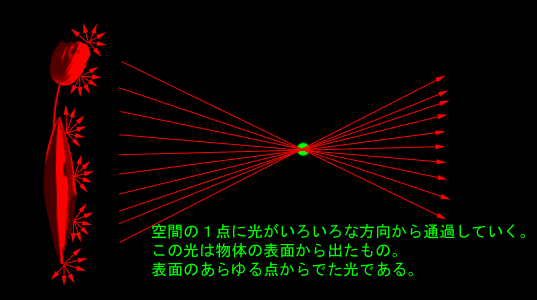
|
|
今度は物体から離れた空間の1点を注目してみよう。 その点には物体の表面のあらゆる点から飛び出た光が通過していることがわかる。 上図の緑の1点は特別な場所じゃないよ。 あなたの目の先、あなたの指先、どこの1点へも物体から飛び出した四方八方の光が通過しているんだ。 目の前の1つの点には、ものすごい数の光があらゆる方向から通過していることがわかったかな。 そう、空間には光があふれている。しかもいろいろな方向を目指して障害物にぶつからない限り、どこまでも進んでいくんだ。 どうだい。空間を進む光のイメージが頭の中にできてきたかな? これが立体画像としてのホログラフィを学ぶ大事なことなんだ。 わからない点は遠慮なくメールくれよ。質問にはわかる範囲で答えるし、講座に反映させるからね。 では、次の講座を楽しみにしてちょうだい。 |
|
初めて書いた日 2001年 2月15日 図と説明を少し変更した日 2001年12月11日 著作権は有限会社アートナウにありますので、勝手に転載しないで下さい。 |